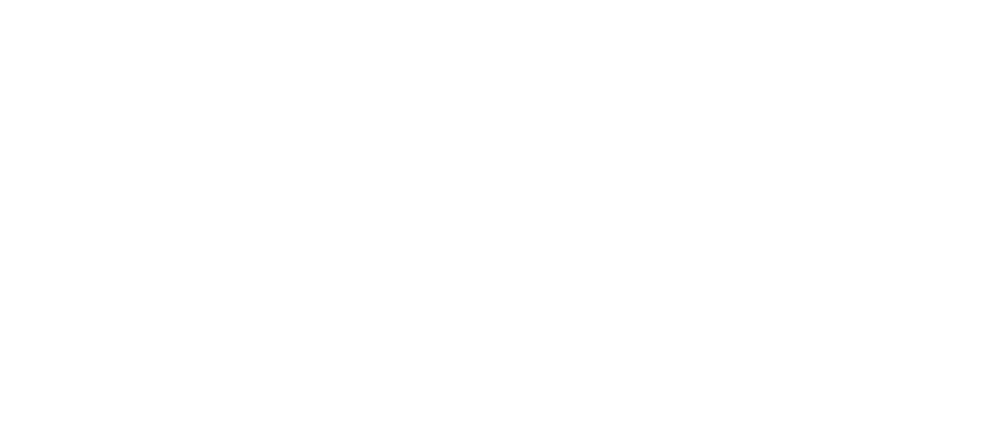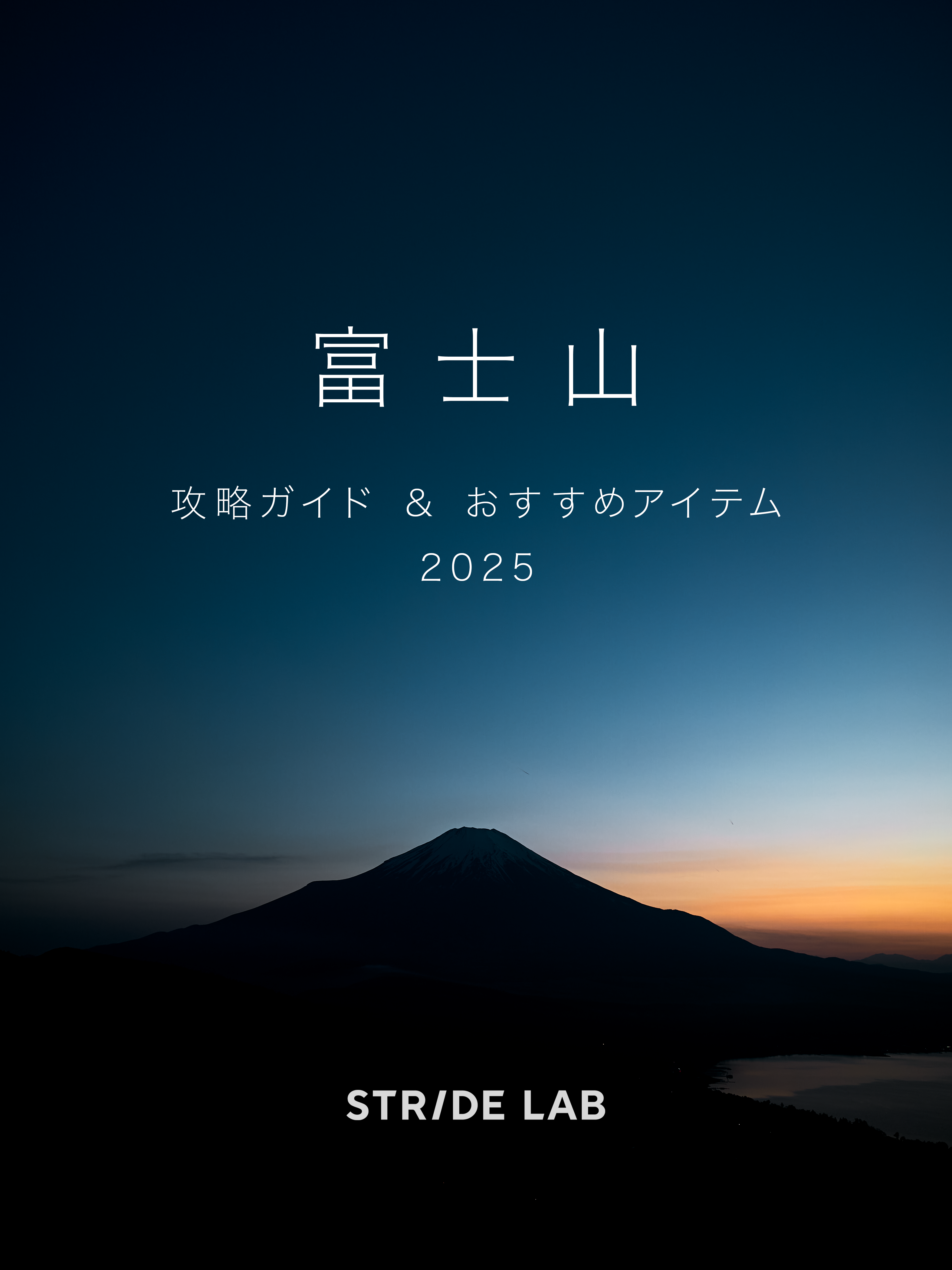ハイカー根津のHIKER'S DELIGHT Vol.5「ハイキングもULもカラダが資本」



ここ2回、UL (ウルトラライト) に焦点をあててきたが、また「ハイキング」に話を戻したいと思う。もちろんULも含まれる内容だが、あくまで軸足は「ハイキング」である。
そもそもこの連載は 『Hiker's Delight』 というタイトルが示すように、ハイキングの魅力や楽しさを伝えることが出発点だ。ただ、ハイキングは個人の遊びであり、楽しみ方も人それぞれ。どう楽しむかに正解も不正解もなく、誰かのスタイルにケチをつけるつもりはまったくない。
僕がこの連載で語る内容もひとつの主観的解釈やアプローチにすぎないので、小説や音楽、映画と同じく、共感する人もいれば、ピンとこない人もいて当然だろう。とはいえ、これまでハイキングを批評する人があまりいなかったからこそ、僕が発信する意義はあると考えている。ただし、主観だけに頼っていては伝わる範囲も限られる。だから前回、前々回のように、僕自身の思いとは切り離して「本質」や「原理原則」に立脚した視点も伝えるようにしている。
日本においては、ハイキングという言葉や行為がここ10年くらいで急速に広まってきた。その一方で、ハイキングの本質や前提条件については、あまり語られてこなかった。だからこそ、いま一度「ハイキングって何なのか?」を問い直す必要があると感じているのだ。

「心・技・体」より「体・心・技」。
.......と前置きが長くなったが、ここからが本題。今回はとてもシンプル、「カラダが大事だよ」という話である。
武道やスポーツの世界ではよく「心・技・体」という言葉が用いられる。とくに武道をはじめとした「道」の世界では、まず心構えや精神面が第一に考えられ、「心→技→体」の順が大事だとされることも多い。

だが元プロ野球選手のイチロー氏は、ある対談で心技体の順番の話になったときにこう語っていた。
「僕も体が最初なんですよ。体→心→技かな。体が重要。これがないとモチベーションが上がらないですよ。これが崩れてたらそもそもやる気が起きない」
「体があってはじめて残りのふたつが活きてくるという感覚がある」
彼にとっては、カラダこそがもっとも重要であり、すべての基盤なのだという。
僕はこの考え方にすごく共感している。というのも、自分自身も長年ハイキングを通じて、「いちばん大切なのはカラダだ」と実感してきたからだ。
ハイキングは、そのフィールドが街中ではなく自然や山であるがゆえに、リスクがつきまとう。とくに日本は、地形が急峻で山深い場所も多く、ある程度の体力や筋力は必要不可欠である。
ハイキングは「安全なお散歩」ではない。
にもかかわらず、そのあたりがあまり語られないまま、ハイキングという言葉と、その心地よいイメージばかりが、時流にのって浸透してしまった。連載のvol.1で僕はこう書いた。
「ハイキングは誰でもはじめられるけれど、それなりの体力・知識・技術が必要になる。もちろん、それらは後付けでも構わない。楽器と同じで、買っただけではうまくならないし、楽しくもならない。ハイキングも練習や準備が必要だ」。

そもそも、ハイキングは「万人にとってやったほうがいい行為」というわけではない。インドア派の人は一生やることがないかもしれないし、だからといって人生を損しているわけではまったくない。
ハイキングは万人に門戸は開かれているが、決して万人向けの「安全なお散歩」ではない。お酒やコーヒーのような嗜好品と似ていて、無理に他人に勧めるものではないし、だれかれ構わず啓蒙するものでもないのだ。
ハイキングとトレイルランニングの相乗効果。
僕は10年ほど前からトレイルランニングをはじめた。もともと走る人間ではなかったのたが、ハイキングを通じて自然や山に魅了されるうちに、フィールドを同じくするトレイルランニングにも興味を抱き、走るようになった。
同じフィールドを歩くのではなく走るトレイルランニングは、ハイキング以上に体力を要する。そのためトレイルランナーの多くは身体能力を高めようとする意識が芽生え、多少なりともトレーニングの必要性を感じ、個人差はあれど練習や鍛錬を行なうようになる。

僕の場合、それが奏功して、ハイキングをしたときに以前よりもラクに感じるようになった(疲れにくくなった)。走り方やカラダの使い方も意識するようになって改善もしたので、それが歩き方にも反映されて脚の過度なねじれやひねりから生じる炎症もなくなった。くわえて、たとえば行程が押してしまった際には走って取り戻すこともできるようになった。こうして、ハイキングとトレイルランニングは互いに良い影響を与えるようになった。
振り返ってみると、当時はハイカーとトレイルランナーの間にまだまだ溝があった。「根津はもう走る人だからな〜(笑)」と、走るのを頑として拒むハイカーから冗談交じりに揶揄されることもあった。でも僕は、「走れたほうがハイキングもラクになるし、楽しくなるし、リスクヘッジにもなる。プラスでしかないのに」と内心思っていた。
軽量化の限界を感じた瞬間。
カラダの重要性をもっとも痛感したのは、プロトレイルランナーの石川弘樹さんと一緒に大峯奥駈道(約90km)を2泊3日でファストパッキングしたときだ。
僕はかなり軽量化して10kgに満たない装備。一方、弘樹さんは重いときで12kgほどのバックパックを背負っていた。今回ばかりはさすがに僕のほうがラクに90kmを終えることができるだろう。と思ったが、それは大きな間違いだった。

僕は毎日ヒーヒー言いながら目的地にたどり着いていたのに、弘樹さんは終始余裕の表情。もちろんアスリートと比較するのはナンセンスではあるのだが、「軽さには限界がある。身体能力の高さには敵わない」と、はっきり実感した瞬間だった。
同時に、人間のカラダはすごい、大きなポテンシャルを秘めている、とも思った。自分もさらにカラダに目を向けて、これまでよりも少しでもいいから身体能力を高めれば、ハイキングはもっと楽しくなるし、もっと自由になると確信した。
ULでも昔から語られていたカラダの重要性。
ULに関して言えば、「軽くすれば体力がない人でもハイキングができる」という観点から、ULが“弱者の戦略”として語られることがある。たしかに一理あるのだが、あくまでそれはULの副産物でしかない。
前回の記事でも引用したグレン・ヴァン・ペスキの言葉 「最小限の装備でウィルダネスの中に身を置くということは、自分のスキルと、今あるものを使って起こる問題を解決する能力に頼るということだ」は、ULの核心のひとつである。
でも、もしULが弱者の戦略になってしまったら、それは自分ではなく、ある意味ギア (軽さ)に頼ることになり、ULの本質からどんどんずれていってしまうことだろう。

BPL (Backpacking Light) のポッドキャストより。(https://backpackinglight.com/podcast-014-training-for-backpacking/)
レイ・ジャーディンは著書 『PCT Hiker's Handbook』で、序盤の21ページ目から6ページにわたって「TRAINING」 というチャプターを設けてその重要性を説いている。
ライアン・ジョーダンは、BPL (Backpacking Light) のポッドキャストでトレーニングのエピソードを配信。序文にも「言うまでもないことですが、バックパッキングをより楽しむには、体の準備ができているかどうかが大きく影響します。では、最適なコンディションに仕上げるためには、どんなトレーニングが効果的なのでしょうか? 今回はそのトレーニングをテーマにお届けします」と書き、具体的なトレーニングメニューまで提示している。
また、グレン・ヴァン・ペスキは、インタビューで「私はエクササイズをしているというわけではないですが、毎日外に出ることを目標にしています。外に出るというのは、最低でも3 mile (4.8km) 歩くことを意味しています」と語っている。
ULの先駆者たちも、カラダの重要性を強く認識しているのである。
ハイキングにおいて「カラダは道具」。
僕はハイキングにおいて「カラダこそがもっとも重要な道具」だと考えている。カラダという道具を磨けば磨くほど、ハイキングはラクになるし、より楽しくなる。
多くのハイカーは、最新のギアやウェアには強い関心を抱く一方で、ハイキングにおいてもっとも重要な「自分のカラダ」には無頓着だったりする。一つひとつのギアの重さを計測したり、素材の特性を正しく理解したり、製品のレビューをしたり、試行錯誤を重ねて道具を使いこなせるようになったりする人はたくさんいるが、自分のカラダのスペックを把握し、それを磨こうとしている人はあまりいない。この傾向は、業界やマーケットがながらく商業的な側面を重視し、装備を中心に訴求してきたことに起因しているのだろう。

自分の身体能力を知るために、VO2MAX(最大酸素摂取量)などを測定。ギアのスペックを知ること以上に、自分のスペックを知ることは大切。東京は聖蹟桜ヶ丘にあるTREATにて。
ふと自動車の進化とも重なる部分があるような気がした。現代の自動車は、自動ブレーキや自動運転のように、ドライバーの技術を補完する方向に進化している。結果として、安全性は向上したがドライバーは技術を磨こうとはしなくなった。ハイキングでも、ギアが進化し軽量化が進むことで「体力がなくても歩ける」ようになり、ハイカーが身体能力を上げようとしなくなる。
車が日常生活に不可欠で(あくまで交通手段としての車)、基本的に毎日同じようなルートしか運転しないという人であれば、技術を磨く必要はないだろう(とはいえ免許制度があるので最低限の技術と知識は備わっている)。
一方で、ハイキングをはじめた人の多くは、次第に行きたい山やトレイルが増えていく。最初は低山の日帰りだったとしても、次はもっと高い山、今度はあの縦走路でテント泊.....と、自然とステップアップしていくものだ。そのときに身体能力が初期のままだと、どうしたってリスクだけが増していく。もちろん1年経っても2年経っても高尾山の1号路しか歩きません、というのであれば体力向上の必要はないかもしれないが、そんな人はごく稀である。
僕は、なにもアスリートになろうと言っているわけではない。ジムに行こうと言っているわけでもない。ただ、日々少しでも歩くこと(あるいは、なるべく階段を使うとか)、食生活を少し意識することくらいはしようよ、と思っている程度である。トレーニングというより、メンテナンスあるいはチューニングと言ったほうがいいだろう。
ハイキングをより自由に、より楽しむために。ハイキングはカラダが資本。これからも僕は、これを大事にしていきたいと思う。


根津 貴央Takahisa Nezu
ロング・ディスタンス・ハイキングをテーマにした文章を書き続けているライター。2012年にアメリカのロングトレイル『パシフィック・クレスト・トレイル(PCT)』を歩き、2014年からは仲間とともに『グレート・ヒマラヤ・トレイル(GHT)』を踏査するプロジェクト『GHT project』を立ち上げ、毎年ヒマラヤに足を運ぶ。著書に『ロングトレイルはじめました。』(誠文堂新光社)、『TRAIL ANGEL』(TRAILS)がある。2025年4月ネパールに移住。現在、カトマンズ在住。